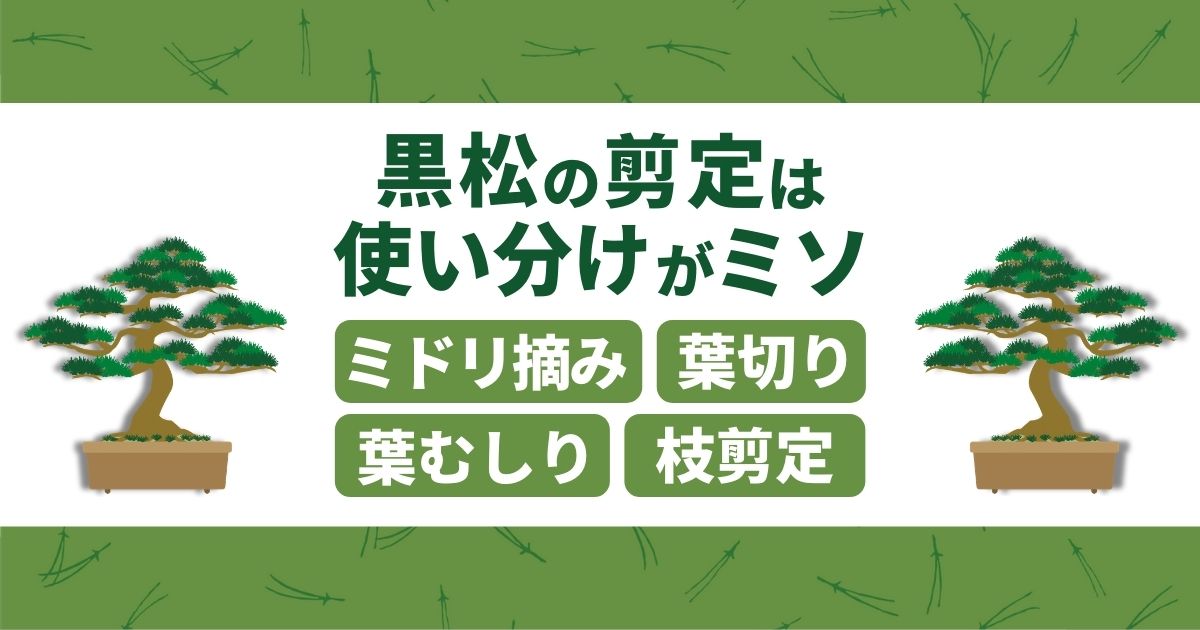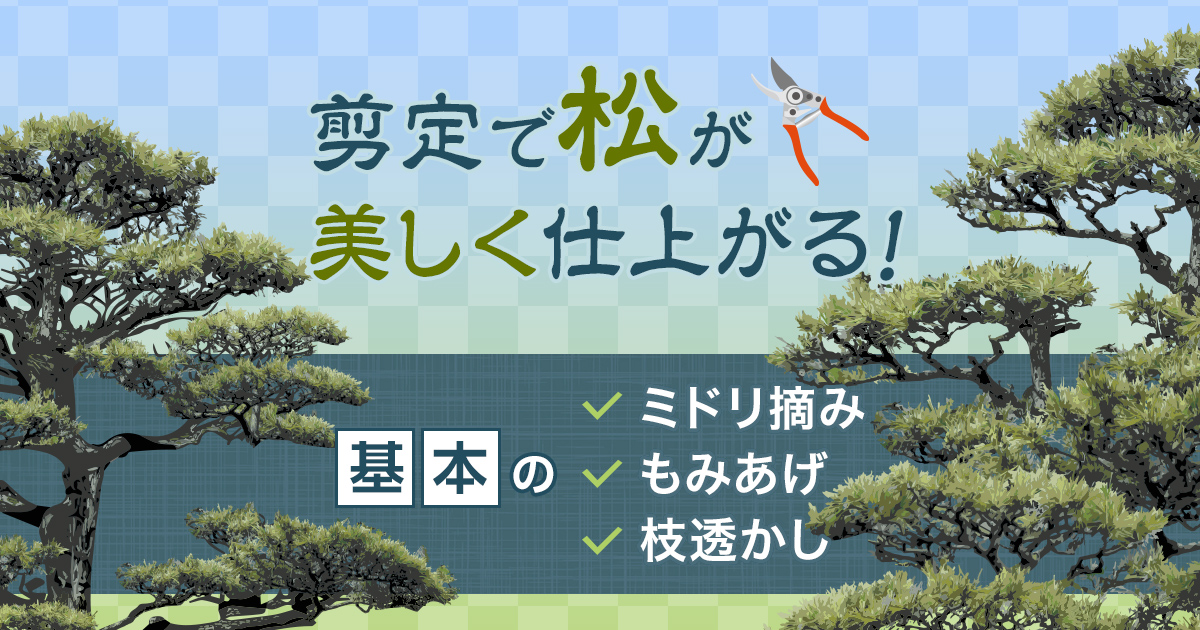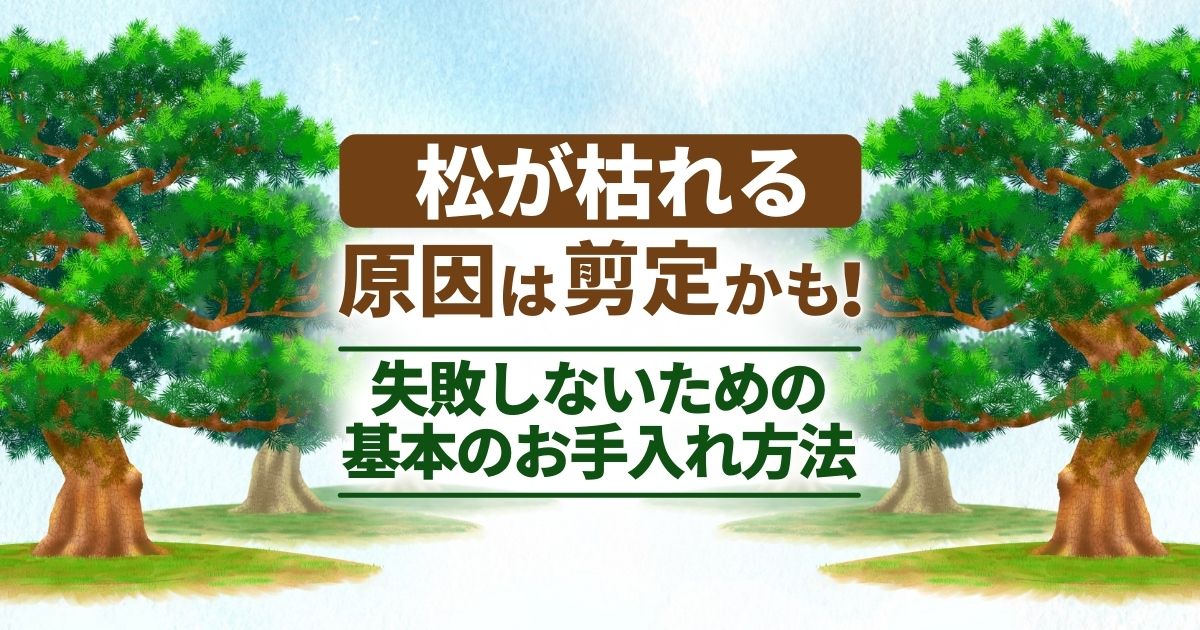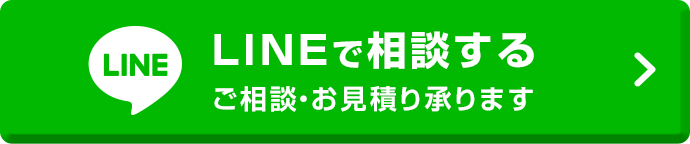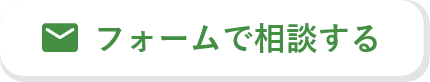黒松はその風情のある見た目から庭木や盆栽として人気の黒松ですが、きれいに維持するには非常に手がかかる樹木でもあります。
松の剪定はプロにとっても難易度が高いため、料金が他の樹木とは別格扱いになっていることもあるくらいです。
しかもミドリ摘みや葉むしりといった松特有の剪定作業に手間がかかるうえ、枝がうねるようにいろいろな方向に伸びるので、
イメージ通りの樹形に仕立てるのが難しいのです。
このコラムでは、庭木や盆栽の黒松に必要な剪定の種類や注意点についてご紹介していきますが、自分で剪定剪定する前に、
一度プロに相談してみるのもおすすめです。
プロに任せると樹形をキレイに整える様子が見られるので、自分でチャレンジする前の参考にもなりますよ。
黒松の剪定方法4種
盆栽でも庭植えでも、黒松に必要な剪定は基本的に同じです。黒松には大きく分けて4つの剪定方法があり、それぞれ目的や適した時期が異なってきます。この章を参考にしつつ、黒松の状態と時期に合わせた剪定をおこなってみてください。
黒松の剪定1:ミドリ摘み

4~5月頃になると、黒松は黄緑色の新芽をつけます。松の新芽のことを「ミドリ」と呼びます。
ミドリは枝の先端に数本つき、やがて枝へと成長して葉が付きます。自然成長に任せておくと
枝葉が増えすぎて見栄えが悪くなってしまうのです。
そのため、成長する前にミドリを適度に間引いて枝の数を抑制します。
ミドリ摘みは、ミドリが柔らかくて摘みやすい5月上旬におこなうのがベストです。この時期を過ぎるとミドリが固くなって、摘むのが困難になってくるので注意しましょう。
ミドリは1つの枝に2~3本程度になるように、手で摘み取っていきます。長いミドリを優先的に摘むと成長後の樹形を保ちやすくなります。
黒松の剪定2:芽切り
芽切りとは、剪定鋏を利用して成長したミドリを根元から切り落とす作業です。黒松は、程よく枝葉を短く留めておくのが一番樹形をきれいに保ちやすくよいとされています。
しかし、春に芽吹いたミドリをそのまま成長させると必要以上に枝葉が長くなりやすく、樹形を乱す原因になってしまうのです。
そこで、6月の終わりから7月初旬頃にミドリを切り落とすと、そこから成長する枝葉が程よい短さになるように調整できます。この方法は、葉を短くさせることから「短葉法」とも呼ばれています。
黒松の剪定3:葉むしり
葉むしりは11月~2月頃におこなう作業で、「もみあげ」ともいいます。枝に付いている不要な葉を手でむしり取る剪定方法です。
枝の根元に付いている葉、下向きの葉を落とすことで枝先に
葉が立ち上がった松らしい姿になり、見栄えがよくなります。
また、余分な葉を減らすことで栄養の分散を防ぎ、風通しもよくなって害虫予防にもなります。
松のもみあげとはのコラムでもポイントを解説していますので、ぜひご覧ください。
黒松の剪定4:枝の剪定
松は太い枝を大きく切ると弱ってしまうので、剪定は「透かし剪定」という方法でおこないます。透かし剪定は、不要な枝を適度に切り落とす軽めの剪定です。
成長期に枝を切るとかえって枝が増えて樹形が乱れるので、枝の剪定は枝葉の成長が止まる10~11月におこなうのがよいです。
透かし剪定は樹形を変えたり整えたりするというより、日当たりや風通しをよくするのがおもな目的です。
樹形を乱しそうな枝や枯れ気味の枝を剪定鋏で切り落としましょう。
松は枝の数が多くそれぞれがバラバラの方向に伸びるので、枝の伸びる方向をイメージして切る枝と残す枝を見極めることが大切です。
詳しくは松の透かし剪定のコツもぜひご参考ください。
黒松の剪定は大変!
黒松は必要な手入れの種類が多く、時期ごとにこまめな管理をする必要があります。繊細な手作業も多く、失敗すると枝が乱れたり枯れたりすることもあるのです。
庭植えの場合も同じで、ある程度大きな黒松であればそれぞれの作業が1日がかりになることもあります。
また、大きな黒松を隅々まで手入れするには脚立を使ったり木に登ったりする高所での作業が必要で、経験や心得がないとケガをしてしまうおそれがあります。
一般的な4脚の脚立はバランスを崩して転倒しやすいため、3脚の剪定用脚立や木に固定して使う枝打ちはしごが必要です。木に登っての剪定はプロでも転落することがある危険な作業なのです。
黒松の剪定が自分でできそうにないと感じたときは、プロの依頼することをおすすめします。
黒松を剪定で失敗しないためのコツ
黒松の剪定には、いくつか注意するべき点があります。剪定をする際は次の点を守って、剪定を成功させましょう。
汚れてもいい服装でおこなう

黒松を剪定すると、粘着性の樹液がでてきます。これは、松ヤニといい塗料や合成ゴム、粘着剤などの幅広い用途があります。
松ヤニはその粘着力から水でもなかなか洗い流せず、一度衣服に付いてしまうと落とすのが困難です。
また、松ヤニが衣服に付くことによってシミになってしまうこともあります。そのため、黒松の剪定をおこなう際は必ず汚れてもいい服装でおこなうようにしましょう。
剪定には成功しやすい順番がある
黒松の剪定は「上から下」「奥から手前」に向かって剪定をするように意識しましょう。
この順番でおこなうことによって、切り落とした枝葉が途中で引っかかったり、剪定中に枝を折って樹形が変になってしまったりすることを予防できます。
「Y」の形を意識する
黒松に限らず、松は直線の枝があると間延びした印象になり、樹形が乱れやすいです。また、枝の先端に葉がない状態にすると枝が成長できなくなります。
そのため、枝分かれしている部分は葉のついた枝を2本残して、先端が「Y」の形になるように枝を切っていくと樹形をきれいに維持しやすくなります。
プロに任せてみる
黒松は枝数が増えやすく、枝はいろいろな方向に勢いよく伸びるので、樹形を維持するのが難しい樹木です。
思い通りの樹形を作るには、枝の伸び方を予測して切る枝や残す新芽を正確に見極める必要があります。
上にご紹介したコツ以外にも、黒松を美しい樹形に整えるには 経験を積まなければわからないことがたくさんあります。
そのため、植木職人は「松の剪定ができれば一人前」といわれるのです。
雄大で力強く伸びる黒松の樹形を作り、趣のある庭木や盆栽を楽しみたいなら、黒松の剪定を長年経験してきたプロに任せるのがより確実です。
プロへの依頼を検討する場合は、松の剪定をプロに頼む費用と業者の選び方もご参考ください。
黒松を育てるために必要なこと
黒松は丈夫な植物ではありますが、育て方を間違えると思うような形に成長してくれないことがあります。そこで、この章では黒松の育て方についてご紹介していきます。
よい苗を選ぶ

よい黒松を育てるためには、よい苗を選ぶ必要があります。黒松の苗を選ぶ際は濃い緑の葉をたくさんつけていて、幹や根がしっかりしたものを選びましょう。
水・肥料
黒松の水やり・肥料やり方法は、盆栽か庭木かによって異なります。しかし、基本的には多くの水と肥料を好む植物であるため、たっぷりと与えてあげましょう。
- 水やり
-
盆栽は1日に1~3回、土が乾いてから水やりをしましょう。庭木の場合は根がしっかり地面に付くまでの2年間は同様のペースで水を与えてください。しっかりと根付いたあとは、雨水だけでも十分育ちます。
- 肥料やり
-
盆栽の場合は、枝葉の成長する4~11月にかけて油カスや骨粉などの固形の有機肥料を与えましょう。庭木の場合は1~2月の間に、根本を掘って有機肥料を与えてください。
針金掛け
針金掛けは黒松を盆栽で育てる際に、幹や枝に銅線などをまいて理想の樹形に矯正する方法です。針金掛けは、休眠期である12~1月の間におこないましょう。
植え替え
盆栽で黒松を育てる場合は、根詰まりに注意しないといけません。根詰まりとは、鉢のなかで根が育ちすぎて水や養分をうまく吸収できない状態です。
根詰まりを防ぐためには、定期的に植え替えをしてあげえる必要があります。
枝や幹が折れてしまわないように注意しながら鉢から黒松を抜き取り、古い根を鋏で切ったあとに新しい鉢に植え直しましょう。若木は2~3年に1回、老木は3~5年に1回のペースでおこなってください。
病害虫対策
マツ科の植物には、すす葉枯病や赤斑葉枯病、アブラムシ、毛虫などさまざまな病害虫が発生します。
病害虫は基本的にじめじめした環境を好むため、葉が密集しすぎないように枝や葉を剪定して、風通しと日当たりをよくして予防しましょう。
松が弱ったり枯れたりしてしまう原因には病害虫の他、生育環境の問題や寿命、剪定の仕方なども関係してきます。詳しくは松が枯れてしまう原因と対処のコラムもご参考ください。
風通しや日当たりをよくする剪定の仕方がわからない、すでに病害虫が発生して黒松が弱ってしまっているという場合は、プロに相談してみましょう。
プロが黒松の状態を確認して適切な処置をすれば、体力が回復することもあります。
黒松の剪定は剪定110番にお任せください!
黒松はその風情のある見た目が魅力的ですが、しっかりと剪定をしないと樹形が崩れてしまったり、病害虫が発生して枯れてしまったりすることもあります。
「黒松を自分できれいに剪定できる自信がない」という場合は、剪定110番にご相談ください。
剪定110番では、黒松の剪定経験が豊富なプロをご紹介しております。見積りは無料となっており、料金をしっかり確認してから依頼できますのでご安心ください。
「しばらく放置していて枝が乱れてしまった」「弱ってしまった」など、さまざまなお悩みに対応できる業者を厳選してご紹介しますので、24時間受付の無料相談窓口にお気軽にお問い合わせください。