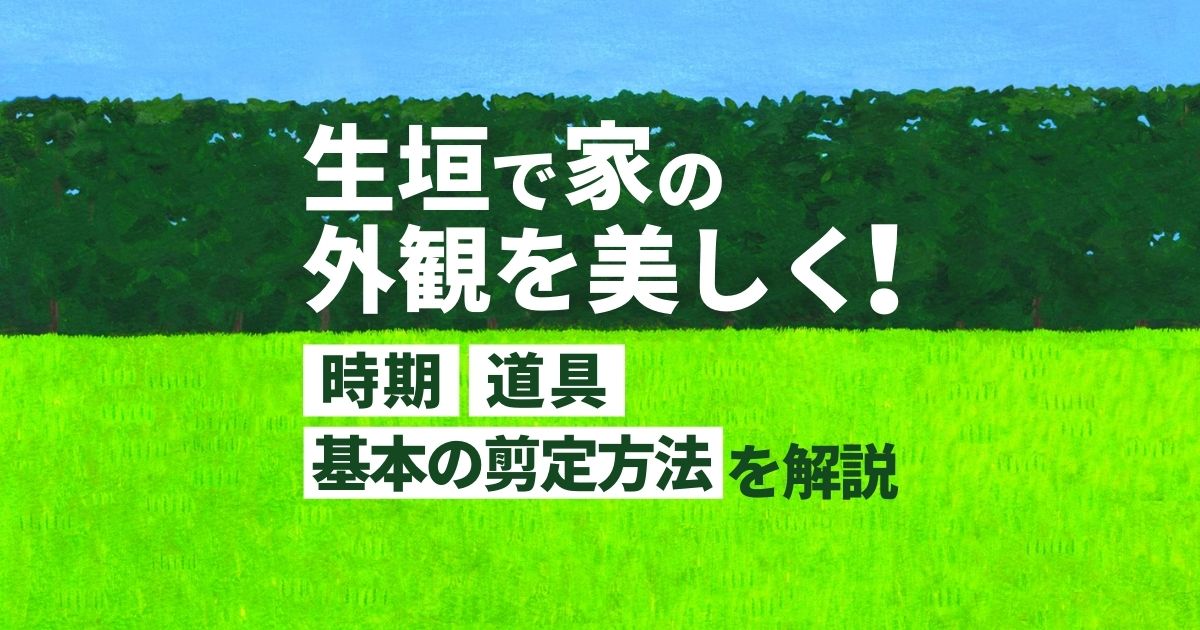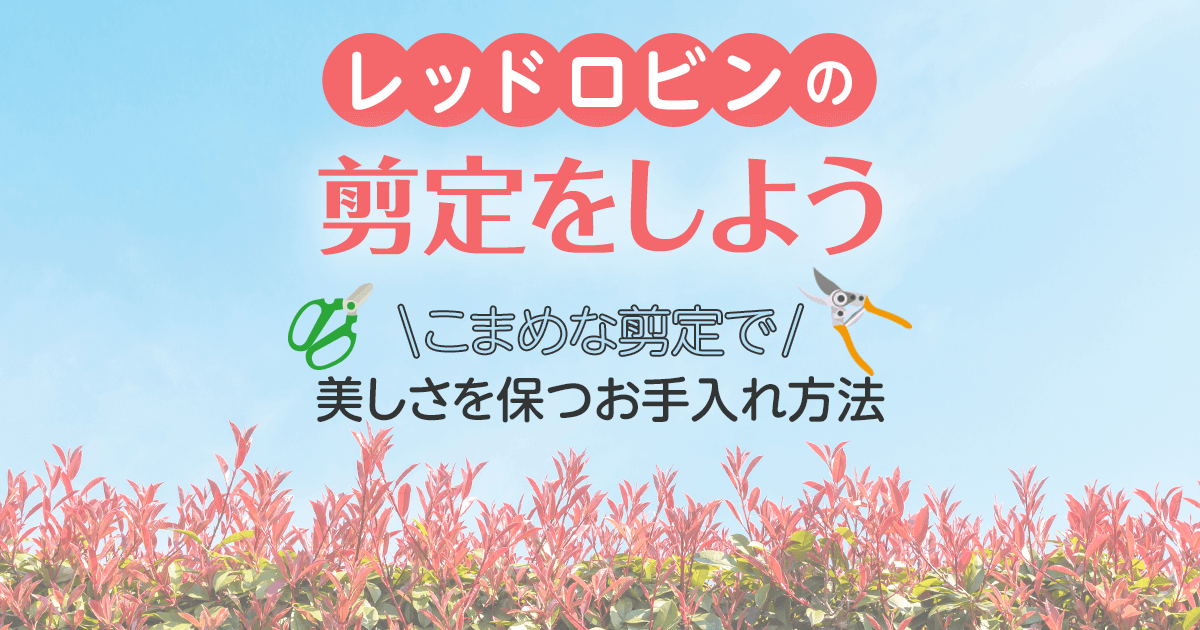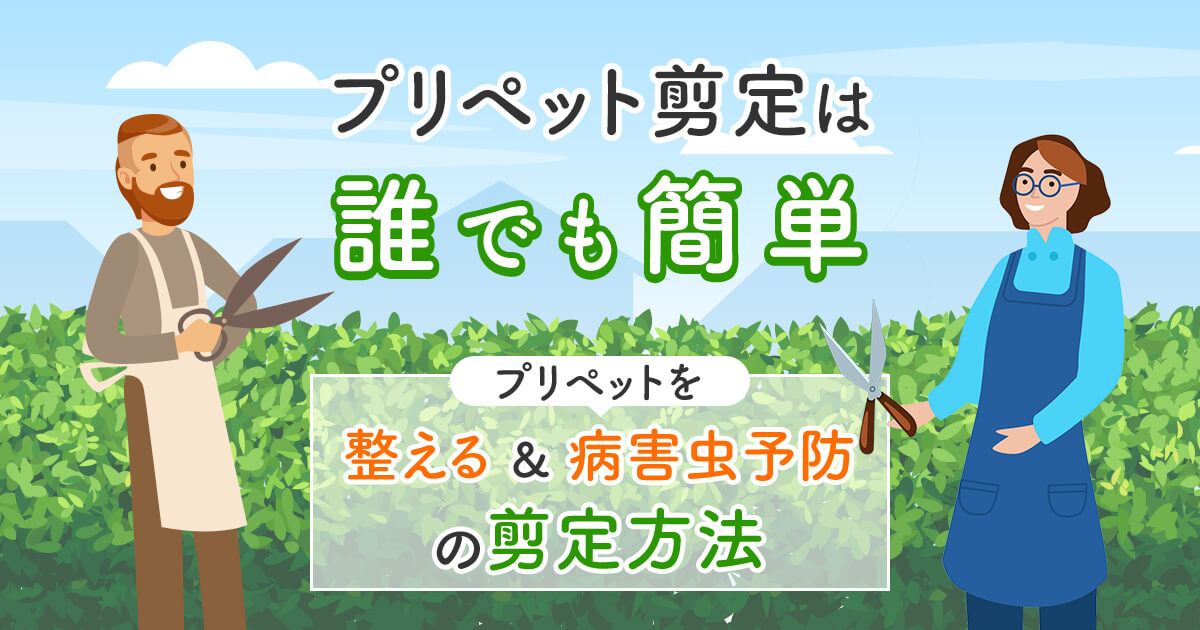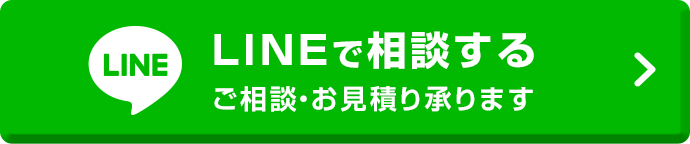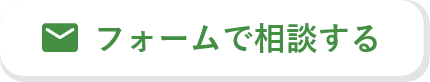生垣は、外からの目隠しや防火・防音・防風といった生活への効果もありますが、敷地の中で最も目につく外周にあるため、枝や葉が伸び放題になっているとどうしても気になってしまいますよね。
そのため生垣をキレイに保つならただ形を整えるだけでなく、切る枝を選んだり、ときには刈り込む必要もあります。
このコラムでは生垣の剪定をするときに知っていただきたい手順やコツをご紹介しますので、今まで生垣の剪定をしたことがないという方もぜひ試してみてください。
生垣の剪定は、樹形をキレイに整えるのが難しいです。なぜなら、刈り込む角度がずれていたり、切る枝を間違えたりすると、すぐに樹形が乱れ、生垣の美観を損ねてしまうからです。
また生垣は、電動バリカン(ヘッジトリマー)を持っていないと、刈り込みバサミで少しずつ樹形を整えなければならないので効率が悪く、重労働になってしまいます。
生垣の剪定作業に自信がなかったり、大変そうとだと感じるなら、まずは一度剪定のプロに相談することをおすすめします。
剪定のプロであれば、広範囲に植えている生垣の剪定はもちろんしっかり形を整えてくれるので、今後自分で手入れをする時の参考にもなります。
垣根・生垣を整えよう!素敵な外観づくりのコツ
生垣の剪定を始める前に、生垣とは一体どんなものか、どのような植物が使われているのか確認してみましょう。
垣根・生垣とは何?
垣根とは、仕切りや目隠しのために施された壁や塀のことを指します。その仕切りや目隠しを植物でつくったものが生垣です。
防犯の観点から、家の目隠しのために敷居を囲むように植物を植える家もありますし、趣味でガーデニングを楽しむほうが家を植物で彩るために植えている場合もあります。
生垣によく使われる植物の種類
生垣に使われている植物は、道すがらよく見かけるものが多いかもしれません。生垣に多く使われる植物には、生垣として選ばれている理由があるのです。ここからは、生垣によく使われる植物の種類を、その理由と共に紹介します。
レッドロビン
レッドロビンは、生垣としてもっとも目にすることが多い樹種ではないでしょうか。季節を問わず赤い新芽が伸びてきますので、1年をとおして赤い葉色を楽しむことができます。すぐに新芽が伸びてきますので、もし剪定に失敗したとしても安心です。
暑さや寒さに強く、耐病性にも優れているので、生垣として選ばれることが多いのも納得ですね。春先には白く小さな花を咲かせますよ。
キャラボク
キャラボクも、よく見かける樹種です。比較的成長が遅く、虫がつきにくく、挿し木によって増やすことのできるキャラボクは生垣にとても適した植物です。成長が遅いことから、狭いスペースに生垣をつくりたい場合にも向いています。
プリペット
プリペットは生垣として人気が高まっている樹種で、見かけることも多いかもしれません。この樹種は成長が早いのでお手入れは必要となりますが、早く生垣を完成させたい方にはもってこいの樹種です。ただし冬には落葉してしまいますので、目隠しとして植える方には向かないでしょう。
その他
昔からよく見かける生垣として、サザンカやマサキ、キンモクセイなどもあります。近年見かけるようになったものには、トキワマンサクやボックスウッドなどがあります。それぞれ成長スピードや特徴の違う木々です。ご自身のお好みや目的、生活スタイルによってどんな木を選ぶのか考えてみるのも楽しいですね。
垣根・生垣のお手入れ方法
暖かな外観と機能性を持ち合わせる生垣ですが、デメリットもあります。それは、植物なので成長するということです。成長する植物を美しく保つには、日ごろのお手入れが欠かせません。
水やり
基本的に、生垣として使う木には水やりの必要はありません。ですが、乾燥に弱い樹種は水やりが必要です。また、土の乾燥が気になる場合にも水を与えたほうがよいでしょう。頻度は多くなくてもよいですが、定期的に水やりをおこないましょう。
肥料
木を植え付ける際、掘り返した土にゆっくりと効果の出るタイプの肥料を混ぜておくとよいです。花や実をつける樹種の場合は、春から秋にかけて多めに肥料を与えるとよいといわれています。
害虫の予防や駆除
弱っている木は病気になりやすく、また害虫が発生することもあります。もし害虫が発生した場合には、薬剤を散布して駆除しましょう。
剪定
木は成長するものですので、きれいな形の生垣を保つには剪定が必要です。形を整えるだけでなく、風とおしをよくすることで木の病気や害虫を防いでくれる効果があります。木の健康のためにも剪定をおこなってください。
垣根・生垣の剪定方法

それでは、きれいな生垣を保つための剪定方法について確認してみましょう。剪定というと、とても大変で難しそうだと思う方も多いかもしれません。でも安心してください。ここでは、初心者でもできる剪定について紹介します。
必要な道具
剪定には、作業に適したさまざまな道具があります。スムーズに作業を進めるためにも、必要な道具をそろえておきましょう。
剪定バサミ
小枝を切ったり、伸びた枝を切り揃える際に使います。剪定バサミにはバイパスタイプとアンビルタイプの2タイプがありますが、刃が両側についているバイパスタイプは切り口がきれいなので細かい剪定に向いています。
そして、刃が片面だけについているアンビルタイプは太い枝でもしっかり切り落とす万能タイプです。使い方は、普通のハサミと同様です。太い枝を切る場合は、奥に押し込むように回しながら切ると簡単に切ることができます。
植木バサミ
指を入れる部分が大きい形状をしています。細い枝を切り取ることができるので、盆栽の剪定にも向いています。剪定バサミのように刃が開くためのバネが入っていませんので、長時間使用しても疲れません。
さまざまなサイズがありますので、自分の手に合うものを選びましょう。細い枝の場合は刃先を使って切り、太い枝の場合は刃の奥のほうで回すように切ると簡単に切ることができます。
刈り込みバサミ
持ち手が長く、刃の部分も細長い形をしています。複数本の枝の長さを一度で整えることができるので、全体の形をつくっていく際には、このハサミが必要です。刃の部分が長いので、茂みの中の葉を切る際にも便利です。
刈り込みバサミは普通のハサミとは違い、切り方にコツがあります。片手は柄を持って固定し、もう片方の手で刃を開閉するように切りましょう。
剪定ノコギリ
片側のみ刃があるノコギリを選びます。双方に刃がついていては、切るつもりではない枝まで切ってしまうことがあるかもしれません。先マルとも呼ばれる刃の先端が丸くなっているタイプのものを選ぶと、ケガのおそれが減ります。
さまざまな長さのノコギリがありますが、25~30センチメートル程度のものが使いやすいでしょう。また、大工用のノコギリは用途が違いますので剪定には向きません。きちんと剪定用のノコギリを用意しましょう。
軍手
枝や葉を切る際には、必ず軍手を装着しましょう。とがった枝の先などは思った以上に鋭利で、ケガをする可能性があります。切り落とした枝や葉を片付ける際にも、軍手で手を保護してください。
脚立や梯子
背が高く、手が届きにくい木を剪定する場合に必要です。アルミ製のものを選ぶと、軽くて持ち運びに便利です。
電動バリカン(ヘッジトリマー)
電動バリカンは枝や葉を切り落とすのに力を使うことがないので、剪定作業をとても楽にしてくれます。電動式や充電式・エンジン式などさまざまです。ハサミよりもコストがかかりますが、レンタルするという方法もあります。1泊2日で3,000円程度がレンタル料金の目安です。
詳しくは最低限必要な剪定道具をまとめた記事をご覧ください。
剪定方法
道具をそろえたら剪定してみましょう。今回は電動バリカンを使用しない、人力での剪定方法の手順を簡単に紹介します。
【手順1】側面から刈り込んでいく
基本的に、刈り込みは下から上へとおこないましょう。一般的な木の特性として、下枝のほうが上枝よりも発芽力が弱いため、必要以上に下枝を刈りこんでしまうと木が枯れてしまう危険があります。下部の剪定は控えめにおこなってください。
太くて生長の早い上部の枝や幹は、しっかりと剪定していきましょう。横に広がって成長する樹種の場合は、横幅をそろえることも大切です。
【手順2】上面を平らに刈りこむ
側面の刈り込みが終わったら、次は上面です。なるべく平らに刈り込むことを意識しましょう。高すぎるとさまざまなトラブルの原因になる可能性がありますので、目隠しとしての生垣の場合は2メートル前後がよいです。
【手順3】枝を透いて風とおしをよくする
枝が混みあっていると、風とおしが悪くなったり光が入りづらくなります。木の病気や害虫の発生の原因ともなりますので、形を整えた後は、枝を透くことで風とおしをよくしましょう。透くときには、成長の早い枝や内向きに伸びた枝を選んでください。
垣根・生垣の剪定を成功させるコツとは?
垣根・生垣の剪定にはいくつかのコツがあります。ご自身で剪定をおこなう場合、以下のようなポイントに気をつけましょう。
剪定時期が大切
剪定は時期が大切です。剪定の時期を間違えてしまうと、花や実を楽しめないだけでなく、木を弱らせてしまうこともあります。一般的に、落葉樹の剪定は落葉中の晩秋以降がよいでしょう。芽吹く前に終わらせてしまいたいので、3月頃までに剪定を終わらせておきたいです。
常緑樹の剪定は、新芽の前の3月下旬から4月ごろです。その次のタイミングは、新芽が成熟して固まる7月から8月、そして次に10月から11月とされています。樹種によってベストな剪定のタイミングは異なりますので、生垣の樹種の剪定時期をしっかりと確認してみてください。
詳しくは剪定時期の解説記事をご覧ください。
正しい枝の切り方とは
剪定の際も、ただ枝を切ればよいというわけではありません。木への負担を減らし、見た目も美しく剪定しましょう。
まず剪定バサミや植木バサミで枝を切る際には、芽や枝のすぐ上で切るようにするのがコツです。長く切り口を残してしまうと伸びていく枝に枯れ跡が残るため、枯れ込みの原因になってしまうことがあります。また、切る際に芽がどちらを向いて付いているかもよく確認してみましょう。
内向きについた芽の上で枝を切ってしまうと、芽が立ち枝ぎみになってしまいます。立ち枝ぎみになってしまうと、横に広がるべきところが真っすぐに伸びてしまうので、樹形を崩す原因となってしまいます。外向きについた芽の上を切るのがよいです。
ただし、剪定は一度間違えてしまうと後戻りができません。どこを切るべきか迷いがある方は、一度剪定業者に相談してみることをおすすめします。
剪定時の注意

剪定時に気をつけたいのは、木を傷つけてしまうことです。枝の切り落とし方によっては木にダメージを与えてしまう原因となります。
木を傷つけない枝の切り方とは
木を切る際に気をつけなければならないのは、芽を傷つけないことです。芽の3~5ミリメートル上を切るようにしましょう。また、太い枝を切る際にも注意が必要です。樹皮が裂けて幹を傷めてしまうことがあります。
太い枝を切る際に気をつけたいのは、切る前に必ず切り込みを入れておくことです。実際に切り落とすところから数センチメートル付け根に近いところに切り込みを入れておくことで、樹皮が裂けていくことを食い止める効果があります。
人間が怪我をすることもあります
木の剪定には刃物を使いますので、怪我のリスクがあるのはもちろんのことですが、木の切り口が怪我の原因となることもあります。
腕を伸ばして遠くの枝を切る場合、「斜め切り」となってしまいます。「斜め切り」だと見た目はきれいなのですが、切り口が尖っていてとても危険です。体にひっかかったり、目をついたりと怪我の原因となるのです。
せっかくきれいに木を剪定できても、怪我の原因となってしまっては元も子もありません。人の体に触れる可能性がある高さの枝は、「斜め切り」ではなく「水平切り」を意識しておこないましょう。
きれいに安全に剪定したいならプロの手を借りよう
剪定方法についてご紹介しましたが、方法をイメージしてみても、いざ実際にご自身でおこなうのは難しい場合があるかもしれません。
必要な道具も、一度そろえてしまえばよいのですが初期投資がかかってしまいます。そういう場合はプロに剪定を頼んでみるのはいかがでしょうか。素早く美しい仕上がりになることでしょう。慣れない剪定で怪我をしてしまうこともありません。
生垣の剪定は剪定110番にお任せください!
剪定110番では、庭木1本の剪定から生垣の剪定まで、あらゆるご相談を承っております。
「生垣をキレイに整えたい」「生垣を自分で剪定したけど失敗した」という方はぜひ剪定110番にご相談ください。
剪定110番では、いつでもお客様からご相談いただけるように、24時間365日対応の無料相談窓口を設けております。早朝や深夜でもお気軽にご相談ください。